
どこの裁判所で裁判したら良いかの戦略を練る
管轄権を有する裁判所に訴状を提出して、民事裁判が始まります。
なお、管轄権というのは、事故発生場所(民事訴訟法第5条9号)、被害者の住所地(民事訴訟法第5条1号・民法第484条)、加害者の住所地(民事訴訟法第4条1項)の裁判所に生じます。弁護士法人小杉法律事務所の場合、管轄権を有する裁判所の裁判官情報を元に訴訟戦略を練り、依頼者の希望とすり合わせながら、どの裁判所に提訴するかを決定します。
学校事故の裁判では誰を訴えることになるのか
民事裁判では、提訴をした方が原告、された方が被告となりますので、被害者側が原告、加害者側・学校側が被告ということになります。
加害者と学校の双方を訴えることもできます。(共同不法行為といいます。)。
体罰が行われたような場合には、教師個人も損害賠償義務を負いますので、この場合は、教師個人も訴えることができます。
なお、学校事故の場合、加害者が児童であるなど未成年ということが多く、この場合、親権者も法定代理人として訴状の被告側に明記します。
民事裁判の期日では何が行われているか
初回期日では、提出した訴状の陳述と、答弁書の陳述がなされます。被告に弁護士が付いたケースでは、形式的な答弁書のみ提出し、初回期日には欠席することが多いです。
そして、第2回期日において、被告の弁護士から訴状に対する詳細な反論を記した準備書面が陳述され、第3回期日において、原告側の弁護士が再反論をするというような流れで、原告側と被告側の反論-再反論というラリーが続きます。
民事裁判は口頭主義に則るべきですので、法廷にて原告側の弁護士と被告側の弁護士が、裁判官を交えて、互いの主張をぶつけ合うのが本来の姿ともいえますが、現状の民事裁判では、書面のラリーが続くのみで、裁判期日は5分程度で終わることもしばしばです。
裁判所和解案
原告・被告双方の主張と書面による証拠がある程度出揃った段階で、裁判所より和解案が示されることが多いです。
裁判所和解案では、原告・被告双方の主張立証に対する、現時点での裁判所の見解が示され、被告が支払うべき損害賠償額(解決金)が具体的に示されます。
書面で示す裁判官もいれば、裁判の期日において口頭で示す裁判官もいます。
裁判所和解案に、原告も被告も同意するとなった場合には和解成立となり、民事裁判は終了します。
他方で、原告・被告の両方又はいずれか一方が裁判所和解案に同意しないとなった場合には、民事裁判は終了せず、審理が続くことになります。
なお、裁判所和解案に納得しない理由について、証拠に基づき意見した場合、裁判所が和解案を修正してくれることがありますので、和解案を増額するチャレンジをした方が良いケースというのも存在します。
尋問・判決
和解が成立しなかった場合には、判決に進みます。
判決に進む場合は、判決前に尋問が行われるケースがあります。
過失割合や責任原因に争いのあるケースでは、原告・被告双方の尋問が行われることが多いです。
尋問の結果を踏まえて裁判所が判決を書きますが、尋問後に裁判所和解案が出されるケースもあります。
判決に対しては、判決書を受け取った日から14日以内に控訴をすることができます(民事訴訟法第258条)。


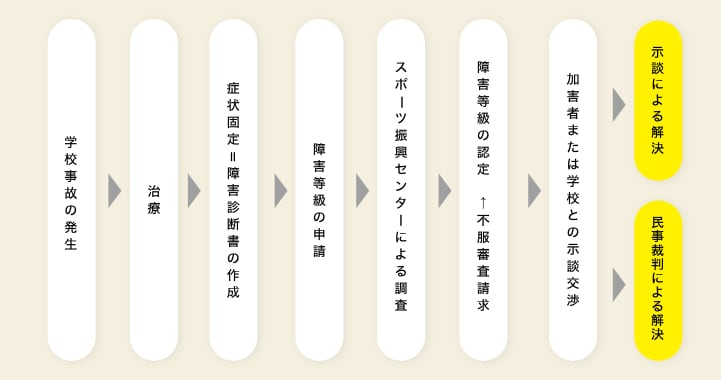
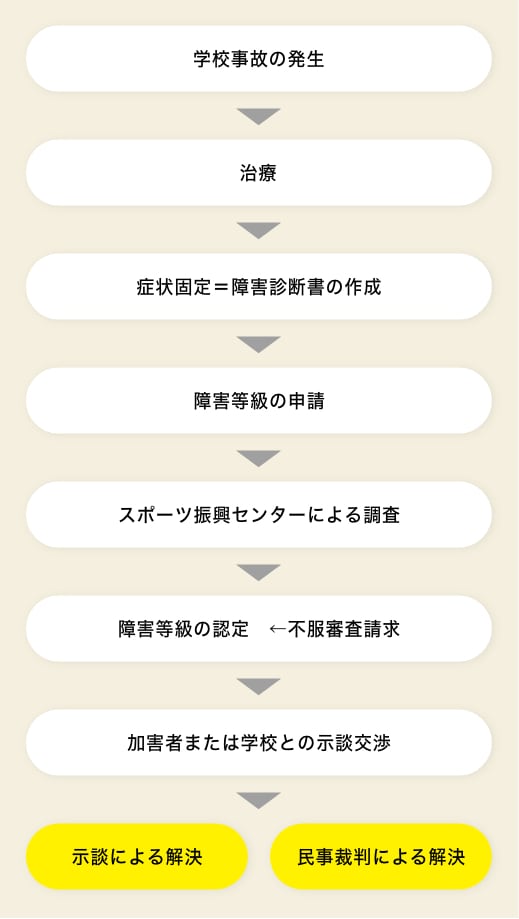



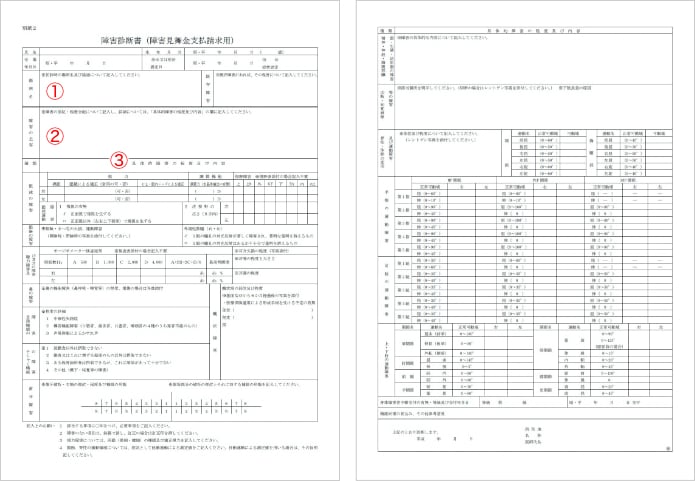

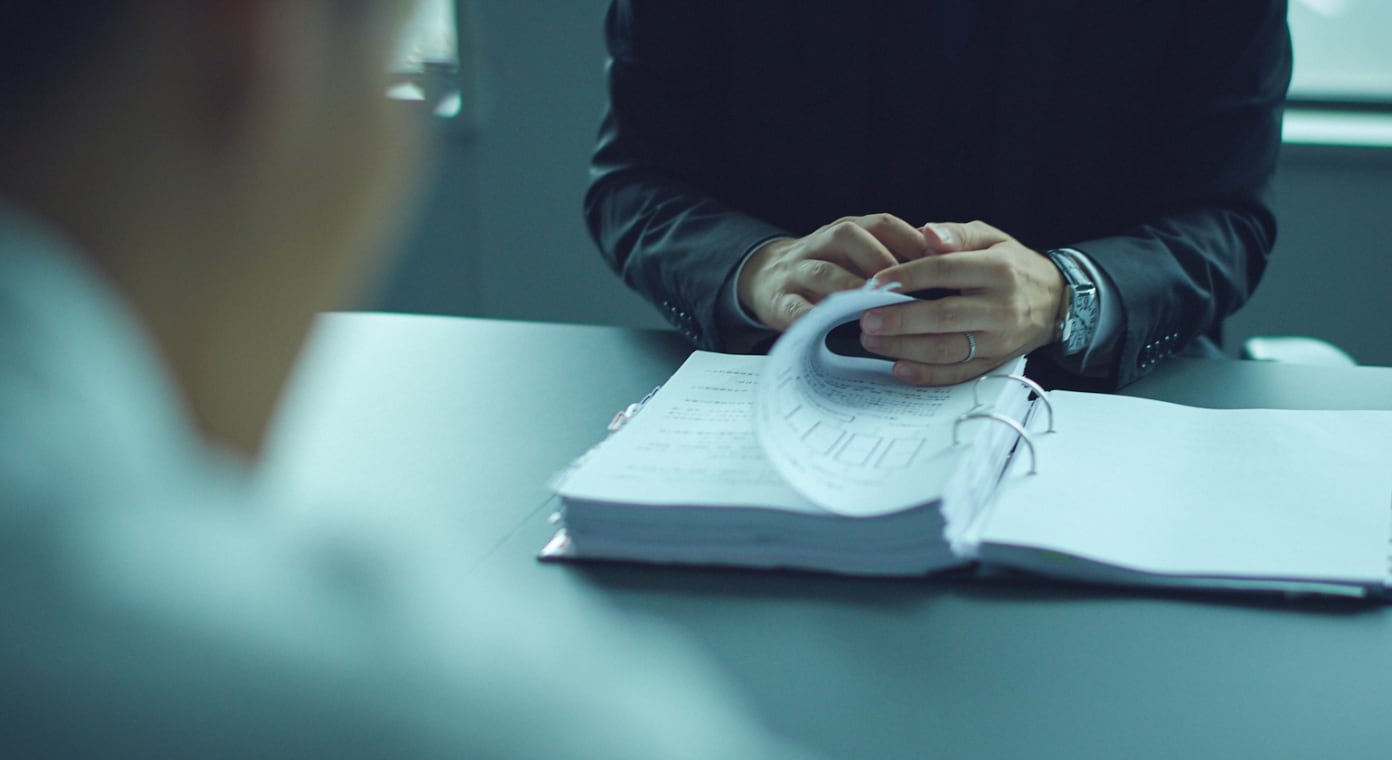
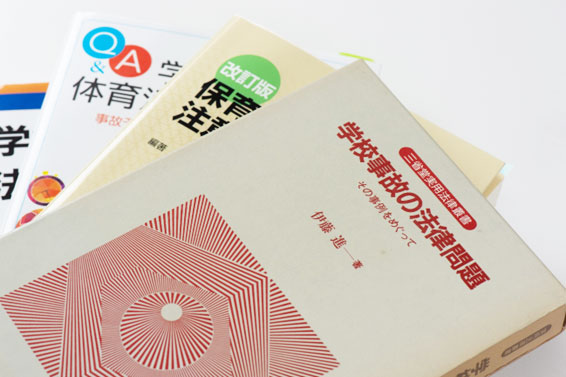




 弁護士
弁護士